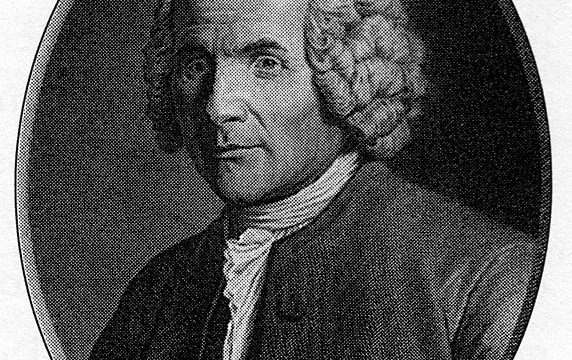2017年5月10日 火曜日 曇り
チャールズ・ディケンズ クリスマス・ストーリーズ 田辺洋子訳 渓水社(けいすいしゃ)2011年(原著は1850年から1867年までのクリスマス特集号)
訳書の原本はエヴリマン・ディケンズ版 Charles Dickens, The Christmas Stories, ed. Ruth Glancy (1996)
田辺洋子 解説:「クリスマス・ストーリーズ」における孤独な旅人 同書の巻末 pp819-829
**
「クリスマス・ストーリーズ」には印象的な四人の孤独な旅人が登場する。即ち、「七人の貧しき旅人」(1854)のリチャード・ダブルディック、「柊亭」(1855)のチャーリー、「誰かさんの手荷物」(1862)のミスター英国人、そして「マグビー・ジャンクション」(1866)のヤング・ジャクソン(又の名をバーボックス・ブラザーズ)という。彼らはその不明な名に象徴される通り、空白の過去を引きずりながら何かを断ち切るために、或いは何かから逃れるために、孤独な旅に出る。旅はもちろん人生の「旅」の表象だが、果たして彼らは何から逃れ、何を求めて、どこへ旅をするのか? そして最終的には何を見出すのか? (田辺、同書、p819)
**
最初に墓地を訪れ、「仮にベベル(=孤児)が死んだら」感傷的に花輪を飾ろう伍長の姿を客観的に想い描いて冷笑していた彼は今や、他者のために命を擲つことをも辞さぬ伍長への真の人間的な敬意を通し、雄雄しくも、自分を失った時の娘にベベルの姿を重ね合わせる。「娘」を失った伍長に自分の姿を重ねるという飽くまで自己中心的な連想の輪を断ち切ったとき、彼は心の殻を一つ突き破ったと言えるだろう。父代わりの伍長を失ったベベルが「父」を再び見出せるとすれば「実の娘」に対して真の「父」たる自分を措いてない。翻せばベベルを「娘」として引き取るためにはまずもって彼自身が真の意味での「父」たらねばならない。・・・(中略)・・・今や自らに課した目的を果たそうとする、或いは自己の取るべき立場を見極めた、彼の最終的な心の砦の氷解の軌跡はそれまでは単に窓から眺めていたにすぎない堅牢な要塞を自分の足で一歩一歩、自己の使命たる「我が子」と共に踏み越えて行く過程に鮮明に跡づけられる。(田辺、同書、p824)
**
如何に早く(速く?)訳すかではなく、ともかく訳せるか、の問題だった、「クリスマス・ストーリーズ」は。それくらい難しかった。思わずボヤくこと頻り。「ディケンズってこんなにクドかったかね? 今さらながら感心するよ」「いいじゃないの、いつまでもそんな風に思えるなら」とは母から返って来た意外な言葉。「ん?」どうやら「クドい」を「スゴい」と聞き違(たが)えたらしい。ま、いっか。(田辺、訳者あとがき、同書、p831)
補註 訳者の田辺洋子女史は1955年広島生まれ。1996年の「互いの友」から始まって、この2011年のクリスマス・ストーリーズまで次々とディケンズ飜訳本を出版されている。「ともかく訳せるか、の問題だった」・・原書と突き合わせてみると、田辺氏のおっしゃることはよーくわかる(といいながら、その苦労は膨大で、未熟な私の想像を絶する)。
私がディケンズを読み始めたのは遅く、文字通り「60の手習い」であるが、田辺氏その他、多くの先達の手引きに助けられながら、これから楽しんで読み進めていきたいと考えている。
*****
********************************************