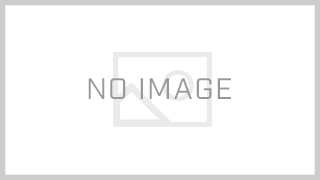2025年3月17日 月曜日 雪
山本周五郎 あとのない仮名 新潮文庫 昭和50年刊(原作は昭和41年6月「別冊文藝春秋」)

・・木や草をあつかうには、生まれつきの「手」というものがある。理由はわからないが、同じ条件で扱っても、その手を持っているのといないのとでは、木や草の育ち方がまるで違う。植木職なかまでは知らない者のないことであり、同時に、それがどうしようもない天成のものであるため、口に出して話すようなことはなかった。(あとのない仮名、同書、p435)
**
補註: 『あとのない仮名』(昭和41年6月「別冊文藝春秋」)山本周五郎さんのほとんど最後の短篇。「このあと山本作品には『おごそかな渇き』(中絶)と『枡落し』の二編があるばかりである。文字通り最晩年の作品」とのこと。
・・ここには過去の己れの精進も無意義なものにしかみえない、からだの中をうそ寒い風が吹きわたっている虚無的な男がいるばかりである。どんなに充実した行動派に思われている人間も、孤独地獄に悩まされることがあるものだ。作者は無間奈落(むけんならく)におちこんだ人間にも限りない愛情を示しているようにもみえる。それとも、過去四十年間、営々と創作活動に打ち込んできた自分自身をふり返ったとき、ふとよぎった無常の思いだったのだろうか。人間の向日性を信じ、事業の不成功を予見しつつも、中道にして斃れるまで、おのれの能力に見きりをつけない人間像を造型し続けた山本周五郎としては、源次はきわめて例外的な人間像だと云える。その意味で『あとのない仮名』は、山本全作品中でも特異な位置を占める作物だということができるであろう。(木村久邇典、同書解説、p484、昭和50年5月)
**
・・「おれの泣きごとはみんな嘘だった、松ノ木もほかの木も、大事な枝を切り落としたのはこのおれだ、植えた木は或るところまでは思うように育つ、秀(ほ)の立ちかたも枝の張りかたも、こっちの思惑どおりに育つけれども、或るところまでくると手に負えなくなっちまう、自分で引いて来て移し、大事にかけて育てた木が、みるみるうちに自分からはなれて、まるで縁のねえべつな木になっちまうんだ」・・
(中略)
・・「木は育つもんだ」と福太が云った、「盆栽ででもねえ限り、植えた木は必ず育ってゆくもんだ、それを庭に合わせて手入れをするのが、植木職のしょうばいじゃねえか」
「それでおらあ職をやめたのさ、自分の手塩にかけた木が、自分からはなれてゆくのを見ちゃあいられなかった、うちをとびだしたのもそのためだ、自分の女房子が自分の女房子でなくなっちまったら、もうおれのうちじゃあねえ、おれと女房子とはもう赤の他人なんだ」
「それなら人別をぬかれたのに文句を云うことはねえだろう」
「むろん文句なんか云やしねえ、ただ、もしかしたらわかってもらえるかもしれねえと思って、話したまでのこった」(山本、『あとのない仮名』、同書、p465-467)
**
補註: 周五郎氏の他作品、長編の「樅の木は残った」、「長い坂」、特に「虚空遍歴」、などの主人公に比べると、この『あとのない仮名』の源次(もとじ、げんじ)は、簡単に虚無的で、ねばり腰が効いていない人として描かれているように思う。周五郎氏がこのような男も描いておきたかったのが何故か、私にはよくわからない。このあとで、何らかの出来事が起こって死にかけていた人間が再起するという物語なら、周五郎文学の中で幾つも思い当たるものがある。たとえば、大人のメルヒェン『あだこ』。顔をまっくろにした「あだこ」が転がり込んでくれば一度死んでいた源次も再び生き返って、それから30年、この世ですっかり禿になってしまうまで、働き者で腕のよい職人として復活する物語にもなろう。これでは物語としてはありふれている。が、現実的にはこちら「あだこヴァージョン」の方が極めて稀なシナリオかと思う。やはり、「あだこ」を待ち望むよりも、自分自身で立ち上がって歩き始める以外には再起の道は開けない。それがこの世の現実だ。さあ、もう一度!
**
*****
*********************************