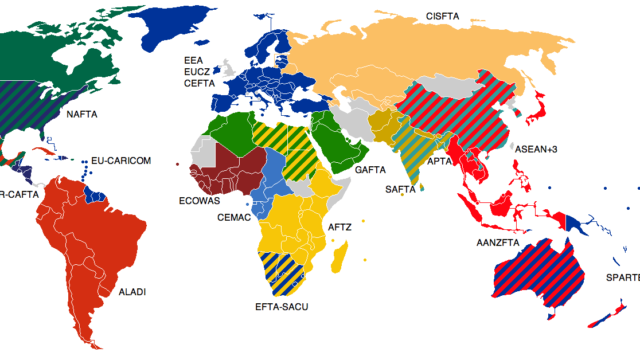2021年3月10日 水曜日 曇り(雪は降るが、またすぐに止む)
山本周五郎 小指 日本婦道記 青空文庫 初出:「講談雑誌」博文館 1946(昭和21)年1月。
<以下引用>
「しかし、それとても不可能なほど困難ではないだろう」けれど新五兵衛の眼には、明らかに困惑の色があった、「……そして平三郎、おまえ八重を娶るという気持に間違いはないだろうな」
「間違いはないと信じますが」
「八重のほうはどうなのだ」
**
八重は面をあげなかった、両手を敷居の上に置いて深く顔を伏せたまま、しかしかなりしっかりした口調で答えた。
「若旦那さまの思し召は、身に余る冥加でございますけれど、本当に勿体ないほど有難うございますけれど、わたくし国のほうに約束をした者がございまして」そこまでいうと、八重の肩が見えるほど震えた。
**
長いあいだ人まかせにしていたし、性分というものがすぐ直るものでもないので、気持の張っているうちはよかったが、少し経つとまた「袴」のようなことがしばしば起った。そういうとき彼の面にうかぶ苦笑ほど寂しげなものはなかった。
――八重、またやったよ。
心のなかでそう呟きながら、彼はよく手を止めてぼんやり何処かを見まもる、「お袴はいけませんですよ」
という八重の顔がふと眼にうかぶ、そこで彼はこう呟く、
――おまえ、心配じゃないのか。
こうして日が過ぎ月が去った。
**
女でなければ理会しがたい心の秘密、女から女だけに通ずる微妙な心理、それがなお女と八重とをじかに結びつけるようだった。
「若旦那さまのお心も……」と、八重は噎びあげながらいった、「……旦那さま、奥さまの思し召も、わたくしには身にあまるほどうれしゅうございました、・・・(中略)・・・でも、……お受け申してはならぬと気づきました、お受け申しては、御恩を仇で返すことになると存じました、もしゆくすえ若旦那さまのお名に瑕のつくようなことでもございましたら、死んでもお詫びはかなわぬと存じまして……」
**
「母上、大きな『袴』でしたよ」といった。そしてなお女が訝しげに眼をあげると、あの柔和な、明るい笑いかたでにこっと笑いながらいった、
「……八重はあの八重だったのですね」
**
補註: 八重はあの八重だったのだ。が、8年もの歳月が流れてしまった。奉公に上がってから5年、それが17,8歳の頃であったとしたなら、それから8年、ついに26歳の当時としては年増の行きそびれ。それを思うと、この小説『小指』の読後、J.オースティンの『Persuasion (説き伏せられて)』を想い起してしまった。似ているような過去の別れを経て、長年の後に再会し結ばれる二人、そのハッピーエンドが二組。
でも、全く正反対の心性の二組。イギリスバロネットのカップル vs 江戸武士とその妻となる女性。オープンに相手を見つめ合うイングランドの美男と才女(もちろんそこそこの美女)vs 迂闊に宙を見つめる江戸の武士(26〜33歳;小姓組で書物番)、眼を伏せ若君の袴の裾を直して支度を手伝う八重(美女という記載無し=美女でなくてよい)。イングランドの女性は眼を上げて正面を見ており、けれど、バロネットの足元をしっかり把握している。一方、川越〜江戸〜川越〜江戸と行って戻ってきた八重は、眼を上げることがない。深く顔を伏せたまま、けれど八重の心は、少し視線を上に向けてずっと遠くを見ていた・・イングランドのバロネット婦女よりもずっと遠くに視線が向けられていたと補註者は思うのである。
*****
*********************************