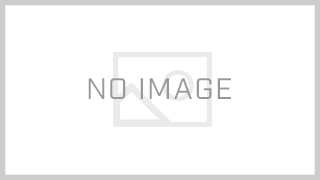2025年3月28日 金曜日 曇り
三浦祐之 増補・日本霊異記の世界 角川ソフィア文庫 令和6年(オリジナルは2010年・角川選書)
・・この時代になって、土地を基盤とした旧豪族層とは別の、貨幣あるいは稲・酒・布など財物の貸付や蓄財、交易による利潤などによる都市型富裕層が出現したことを意味している。そして、それを促したのは、律令国家の経済政策であったのは言うまでもない。
そのことは、「美濃国戸籍」が各戸を資産差によって九等に区分しているとか、献金や献物の額に応じて位階を与えるとか、銭の流通を促進させようとしていたとかいう国家の施策によって窺い知ることができる。そうした時代を象徴するかのように、霊異記には、「南尤、銅銭万貫、白米万石、好女多徳。施したまへ」と祈る、金と女がすべてといった修行僧が登場することにもなるし(上巻第三十一縁)、先にふれた「慳貪」という語がはじめて登場することにもなったのである。(三浦、同書、補講2、p328)
**
・・『日本霊異記』が見いだした心と表現、また山上憶良が題材とし表現しようとした「志」は、その後の文学史のなかでどのように展開したかということについては、追跡と検証を行うことができないままである。はたして、そこに描かれ歌われた家族の生活や心の傷みや生きることの苦しさは、どのように文学史のなかに根づいたのであろうか、あるいはどこかで消えてしまったのであろうか。ここで掬い取られた心は、異種として排除されてしまったように思えるからである。というのは、山上憶良の作品と思想を受け継いで、平安以降の和歌世界はどのような歌や歌人を生みだしたのか、残念ながら思い浮かべることができないのである。また、のちの説話集のなかには、霊異記説話が抱え込んでいた泥くさい生活が見えにくくなっているように思えて残念な気がする。
それは、文学史の主流が貴族たちを中心とした宮廷社会に入り浸ってしまうということとかかわるのではないか。(中略)そこでは、日々の暮らしのなかに生じる貧困や病いの苦しみが取りあげられるはずもなく、個々人の心は埋没せざるを得ない。(三浦、同書補講2、p322)
**
文学史のなかの『日本霊異記』
『日本霊異記』という作品は、日本文学史のなかにどのように位置づけることができるかと尋ねられたら、わたしは、ひとりひとりの心を描こうとしたところに霊異記説話の新しさはあると答えたい。ここでいう心とは、恋しいとか悲しいとかいうような、「比喩化できるできる心」のことではなく、規範化されない個々の人間のありようが試される心のことをいう。そして、そうした心を取り出す手法と表現とを手に入れたのが霊異記説話であったと考えるからである。
比喩化できる心というのは、『万葉集』の相聞歌や挽歌に普遍的に見いだせる共有できる心をいう。それに対して霊異記が描こうとした心は、個別の、具体的な事例によってしか描けない心であり、ひとりひとりが個別に自覚しなければならなくなった心である。なぜなら、善悪いずれの場合も、あの結果をもたらしたのは個々人の行動に起因すると認識されるということは、それぞれの行動は、他者とは共有できない心が生じせしめたものと考えなければならないからである。
おそらく、そうした心の発見は、八世紀という時代の、思想としての仏教と制度としての律令との合わせ技によって可能になった。(三浦、同書補講2、p311)
**
*****
*********************************