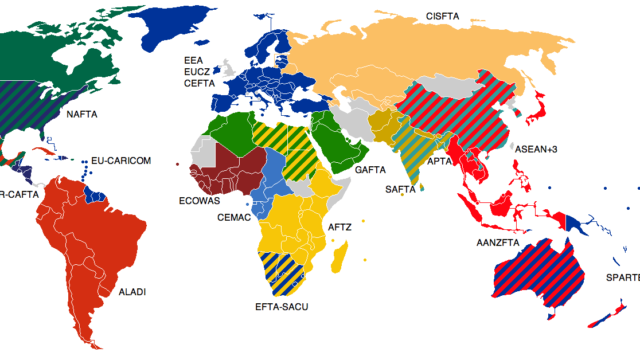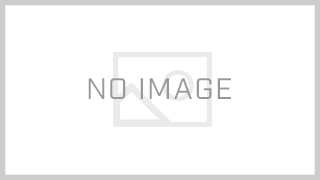2018年3月2日 金曜日 雪
ツルゲーネフ 父と子 金子幸彦訳 岩波文庫 1959年(オリジナルは1862年刊)
**
補註: この小説の内容からも容易に推察されることであるが、小説の題名の「父と子」、父も子も複数形となっている。
**
・・いろいろな、定かならぬ感情、過ぎ去りゆく生活の意識、新しいものへのあこがれ、こういうものに動かされて、彼女みずから強いてあるところまで進んでゆき、そのむこうをのぞいて見たが–そこに見たものは。深い淵ではなくて、空しさ・・あるいはむしろ醜さであった。(ツルゲーネフ、同訳書、p175-176)
**
・・かきとなると、話をしても身ぶるいがでるほどであった。食べることはすきであったが、精進はかたく守った。(ツルゲーネフ、同訳書、p203)
補註: (ロシア語の原文に当たっていただいて、「かき」の意味を確定してもらう予定だが・・)私の暫定的な改訂(漢字を多く入れてみた):
「柿(または牡蠣;補註参照)となると、話をしても身震いが出るほどであった。食べることは好きであったが、精進(補註*参照)は固く守った。」
補註: ここの「かき」が、貝の牡蠣のことか、果物の柿のことか? 平仮名であるために確定できない。広大で海から遠いロシアの田舎でこの時代に牡蠣を安全に食べることが可能であったかどうか、疑わしいので、果物の柿の方かとも思ってみる。しかし、寒いロシアで柿を栽培できるのか(ちなみに北海道では寒すぎて柿は育たない)、柿が(西瓜と同じように)物忌みの対象となりえるのか、物忌みになるとしてその理由は?・・などと考えると、私には到底確定できない。原著に当たってもらう必要がある。柿(または牡蠣)に何か呪術的な禁忌事項があるかどうか、これも問い合わせてみる予定である。
この例でも分かるように、この1959年版の飜訳は、漢字の使い方が少な過ぎるように思う。ある程度まではどんどん漢字を使って書き表した方が、日本語は表現し易く、また読み易くなるのであるが・・。
数多くの漢字を、ワープロの候補に載っているものを単に選ぶだけで自由に使える今は、60年前に比べてずいぶんと楽になっている。ワープロのお蔭である。(旧漢字が選べなかったり、歴史的仮名遣いを打ち込みにくかったりと、不満は多くあるものの・・)。
補註*: 「精進」・・ロシアの正教のご婦人の「精進」の料理や習慣に関しては、イメージが浮かばない。宿題としたい。
**
・・しかし、この瞬間、彼の心のなかには、消えはてた自分の全生涯がおののきふるえていたのである。(ツルゲーネフ、同訳書、p278)
**
ーー姉さんはあのころ、あの人にかぶれていたんです、なたとおなじようにね。
ーーぼくとおなじようにですって! では、君は僕がもう彼の影響から抜け出したことに気がついているんですか?
・・・(中略)・・・
ーーなんと言ったらいいかしら・・あの人は猛獣ですし、あたしや、あなたは飼いならされた獣です。
ーーぼくも飼いならされた獣ですか?
カーチャはうなずいた。(ツルゲーネフ、同訳書、p284-285)
**
・・ここにいると、むすこに、その思い出に近づくことができるかのように。・・彼らの祈りやなみだは、みのりのないものであろうか? いな! どれほどはげしい、罪ぶかい、反逆のたましいがこの墓のなかに隠れていようとも、その上に咲く花は、けがれのない目で、おだやかに人々をながめている。これらの花が人々に語って聞かせるのは、ただとこしえの安静のみではない。「無心の」自然の偉大な静けさのみではない。彼らはまた永遠の和解と、かぎりない生命をも語っている・・(ツルゲーネフ、同訳書、p347-348)
*****
********************************************