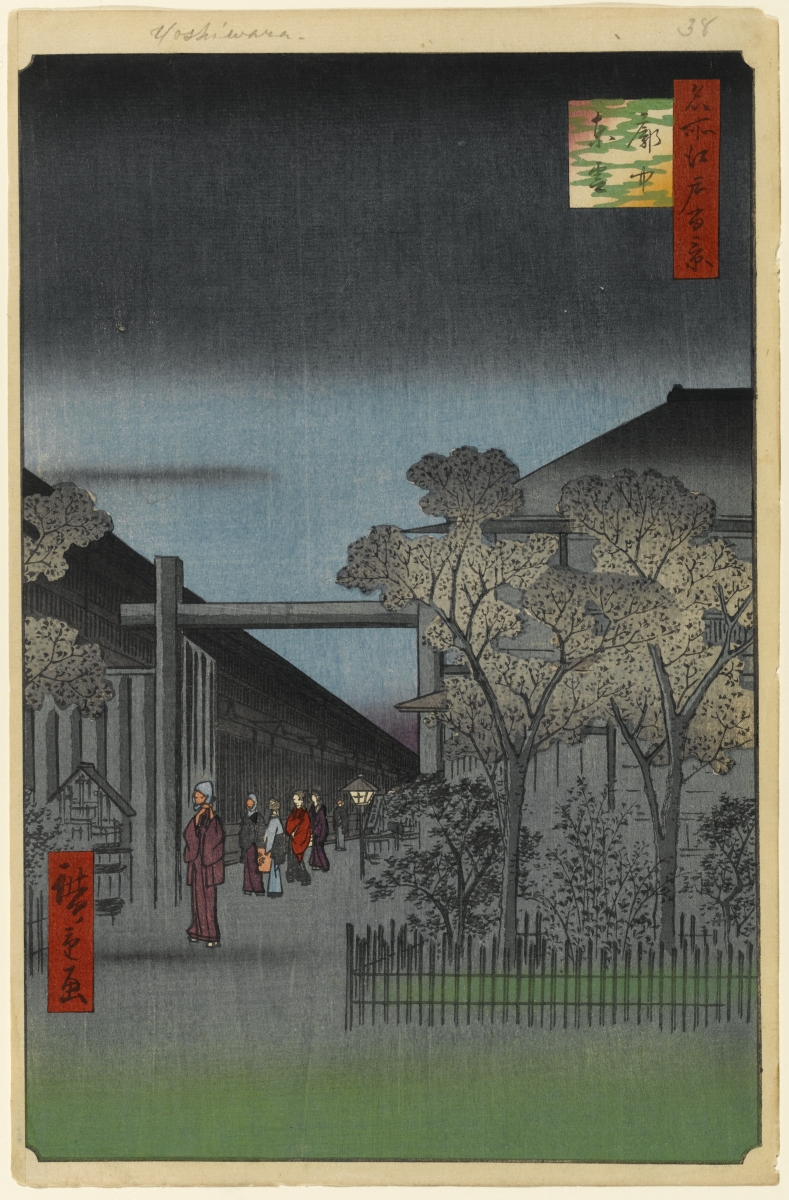2025年4月7日 月曜日 晴れ
三浦佑之 平城京の家族たち ゆらぐ親子の絆 角川ソフィア文庫 平成22年刊(オリジナルの『万葉びとの「家族」誌 律令国家成立の衝撃』(講談社選書メチエ 1996年)を改題・改稿したもの)
・・班田や納税が人々の意識のなかにおおきな影響を与えたのは、その実質的な所有形態や労働はともかく、班田も納税も、「個人」に対して与えられ課せられるものであったということではなかったか。(中略)
・・口分田は家や一族の所有になるものではなく、原則として各個人が所有し耕作し「租」を納めるものとして貸し付けられたのである。これが「律令」の根本理念である。他の税も同様に、成人男子「個人」ごとに課せれられる。おそらく、日本において、人間が個体として認識される最初の出来事だったと云っても大袈裟ではないだろう。
これは、八世紀の家族や親子を考える場合に見逃すことのできない衝撃的な事件だったろう。家族や一族の共有する財としてあった耕作地が一人ずつ所有者が割り当てられ、その人間が死んだら自分たちの所有ではなくなってしまうのである。個体の財の観念は、一般の農民たちにとっては初めての体験だったに違いない。そのことに、精神の問題として個体が最初に認識されることになった仏教思想を重ねて考えてゆくと、そこに八世紀の日本人の考え方を形作ってゆく重要な要因を認めなければならない。そして、この点に間しては、後に読む『日本霊異記』の説話でクローズアップされることになる。(三浦、同書、p170)
**
*****
*********************************