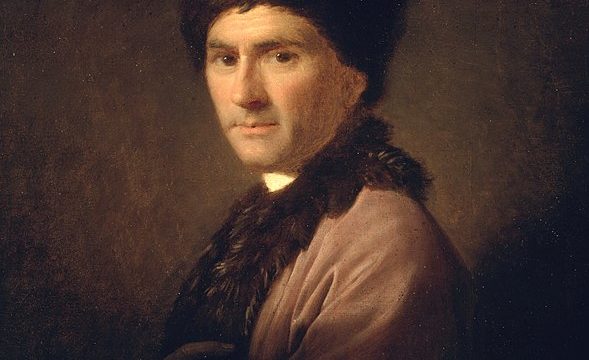2016年4月3日 日曜日 雨のち曇り
白川静 後期万葉論 中央公論社 1995年
憶良:人生の惨苦のうちに、存在するものの姿を直視する老いたる異郷人
憶良・・苦渋にみちた過去を負うて、むしろ人生の惨苦のうちに、存在するものの姿を直視しようとする老いたる異郷人の姿が、あるように思う。・・憶良が渡来者であり、渡来者の文化の伝統の上に立つという牢乎たる意識が、憶良の文学の脊梁をなしている。(白川、同書、p143)
(憶良の)文学を「行路死人歌の文学」と規定する考えかた(大井清民氏「山上憶良」)もあるが、それは老病死苦の問題をも含めて、人生というものを考えようとした歌人の作品の一部として、みることができよう。挽歌を呪歌・儀礼歌として、随所に死霊を鎮める鎮魂の歌を作った人麻呂とは、明らかに異なる立場にあるものであった。ただこの時期の憶良が、人麻呂集団といくらかの関係をもつ、近い位置にいたであろうことは、考えることができよう。(白川、同書、p140)
*****
古と今、初期と後とを截然(せつぜん)として区別するものは、歌が伝統的な儀礼の場、ことだまによる魂振り的な性格からはなれて、文学としての思想性・社会性・日常性というような世界に傾斜してゆくところにある。一般的にいって、この古代性からの脱却に、歌の新しい世界があった。憶良の「日本挽歌」が、その新しい炬火(きょか)の一つであった。憶良(補注1参照)がそれまで、ほとんど作歌らしい活動をしていなかったのは、かれが歌の伝統の中で、自己表現の適当な方法を発見しえずにいたからであろう。ただわずかに「濱松が枝の追加歌」などに、自らのうちに胎動するものを感じていたのであろうが、今かれは、自らのうちにあるものを、明らかに感得し、意識しはじめたようである。それはかれが、深く仏教的な帰依を求めながら、しかも「世間」を脱却することができず、苦悩を続けていた生死の問題に、このときまさしく直面したからであろう。(白川、同書、p146)
百済系のすぐれた仏像
百済観音にしても弥勒思惟像にしても、それは仏の荘厳と権威を示すためのものではなく、宗教者の内省と苦悩とを示すものである。正面から仰いで拝するのでなく、側面観照をも可能にしているその様式は、・・仏像における思想性を追求したもので、それはただ荘厳と権威とのみを追究する国家仏教的な仏像と、対蹠的な形式のものといってよい。・・憶良はおそらく、敬虔な仏教信者であったのであろう。(白川、同書、p148)
*****
補注1
神亀五年(七二八)七月二十一日「日本挽歌」。このとき、憶良はすでに六十八歳、筑前國守。
補注 憶良の「日本挽歌」(巻五、七九四)
*****
憶良の歌は、その異端性のゆえに、「万葉」の中ではむしろ重要性をもつのである。(白川、同書、p273)
**********