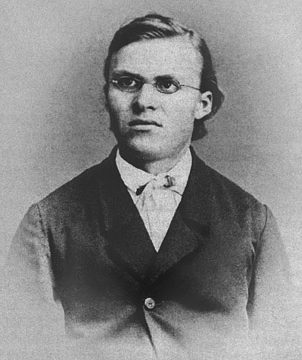2024年12月12日 木曜日 雪
佐藤常雄・大石慎三郎 貧農史観を見直す 講談社現代新書1259・新書江戸時代3 1995年
・・本百姓・水呑という村落内身分は、十七世紀後半に新田開発が頂点に達し、ムラの規模に見合った扶養可能な農民人口数が一定になった段階で発生したものである。ムラに居住する権利としての農民の名跡を保証した本百姓株の固定化が、次三男の分家や非血縁分家などによる新規農民の出現を制限することになったのである。
十七世紀末から十八世紀にかけて、元禄・享保期の村明細帳には、そのムラの構成員として本百姓と水呑の軒数が全国各地で記載されるようになる。なお、江戸時代のムラの平均的な規模は、村高が四百石、農民数が四百人程度である。(佐藤、同書、p96)
・・古代・中世においては、公家・武士などの支配者層のイエが形成されていたが、この時期に至って初めて、庶民のイエが成立したのである。イエのなりわいとしての家業、イエの財産としての家産、イエの村落内外に対する格式としての家格、イエのならわしとしての家訓などの、いわゆる農民のイエ意識の発生である。
つまり、ムラの農民にとっての最大の関心事は、イエの繁栄と維持であり、農民は農業の生産活動にしても日常生活においても、ムラとイエの規範を回転軸として行動をすることになるのである。(佐藤、同書、p96)
**
*****
*********************************