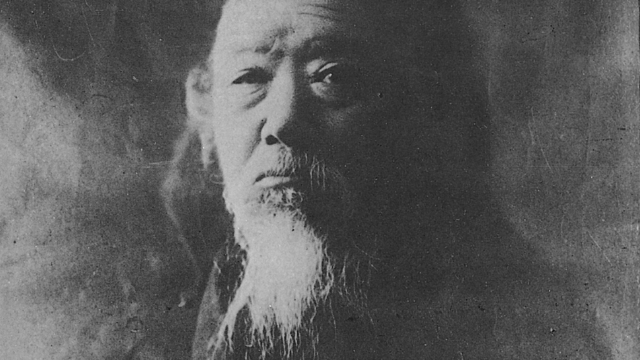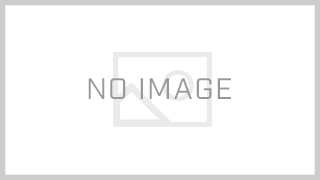2025年2月27日 木曜日 晴れ
三浦佑之(みうらすけゆき)古事記講義 文春文庫 2007年(初出は「文學界」2003年一月号〜四月号、単行本は2003年文藝春秋刊、文庫本は2007年)
・・「高志の」という冠辞がつけられることで、ヲロチには自然神であるとともに異界性を抱えこんで二重化された恐怖が付与されることになります。そしてそこには、高志に対する出雲の側の優越性が語り込められることになったのです。そこでのヲロチは、自然の猛威を象徴した川の神というよりは、制圧されなければならない外部=異世界の象徴コシノヤマタノヲロチとなるのです。
いささか段階論的な物言いになりますが、おそらくそれは、出雲が大和朝廷に服属する前の、王権的なクニ(国)の段階において生じた神話とみなすことができます。古事記のヲロチ退治神話は、そうした段階の出雲の側の論理を抱えこんだままに時間を停止させられた神話なのではないでしょうか。
一方、出雲の側では、出雲国風土記に語られていたように、人間の側の文化としての水の管理=治水技術の起源は、古志(高志)から来た人びとによってもたらされたという伝承をもっていました。繰り返しになりますが、そこに出雲と高志との根源的な関係が示されていたわけです。高志は、出雲の人びとにとって恐ろしい異世界であるとともに、すばらしい異世界でもあったということです。そのために、高志から来るヲロチも、古志から来た人も、ともに洪水や治水にかかわるのです。(三浦、同書、p363-364)
**
*****
*********************************