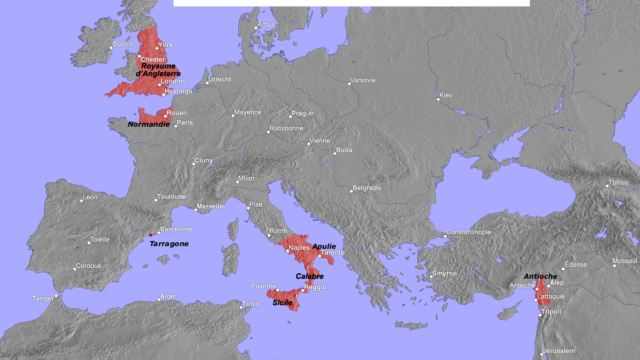2017年3月1日 水曜日 曇り
ジョージ・オーウェル チャールズ・ディケンズ 1940年; オーウェル評論集 小野寺健編訳 岩波文庫(赤・262-1)1982年
**
「オリヴァー・トゥイスト」「過酷な時代」「荒涼館」「リトル・ドリット」などでの英国の社会制度にたいするディケンズの攻撃の激しさは、空前絶後だった。ところが彼のうまさは、そのために憎まれることもなく、それどころか、攻撃された当の人びとがすっぽり彼をのみこんでしまって、ディケンズ自身が体制になってしまったところにある。・・・(中略)・・・ディケンズはあらゆる人間を攻撃しながら、誰一人敵にまわさずにすんだように見える。そうなると当然、彼の社会攻撃にはやはり何かまやかしがあるのではないかと疑いたくなってくる。彼の社会、道徳、政治にたいする立場は厳密にはどうなのか? 例によって、それを見定めるには、まず彼がそうでなかったものを見きわめることから始めるほうが早い。(オーウェル、同書、p53)
1)まず第一に、チェスタトン氏やジャクソン氏は彼が「プロレタリア」作家だと言いたいらしいが、それはちがう。そもそも彼はプロレタリアートのことなど書いてはいないのであって、その点では、過去現在を問わず圧倒的多数の小説家と同じなのだ。(同、p54)
2)第二に、ディケンズはふつうに使われている意味で「革命家的な」作家ではない。ただ、この面での彼の立場にはいささかの説明が要る。(同、p55)
はっきり言えば、ディケンズの社会批判はもっぱら道徳的なものである。だからこそ、彼の作品には、どこを探しても建設的な提言などまったく見つからない。・・注目すべきことは、ディケンズの姿勢が根本において「破壊的」でさえない、という点である。・・というのも、実は、彼の標的は社会ではなく、「人間性」だからである。・・彼が「言わんとするところ」は、一見、総体的に陳腐そのものである。すなわち、もし人間が立派な生き方をしさえすれば、世の中も立派になるだろう、というだけのことなのだ。
こうなると当然、権力のある地位にいて立派な行動をとる人物が少しは必要になる。そこで善良な金持ちという、ディケンズ特有の人物がくりかえし登場することになる。(同、p56-58より抄)・・ディケンズが1850年代に書いたいささか陰鬱な作品から判断すると、その頃の彼は、すでに、腐敗した社会では善意の個人など無力なことを理解していたのだと思われる。(同、p59)
暴力を憎み、政治を信用しないとなれば、のこる唯一の救済策は教育だけである。社会全体は救いようがないかも知れないにせよ、個々の人間については、まだ若いうちに手を打てばかならず見込みがあるのだ。ディケンズが幼年時代に執着するのは、一つにはそのためである。(同、70-71)
**
*****
********************************************