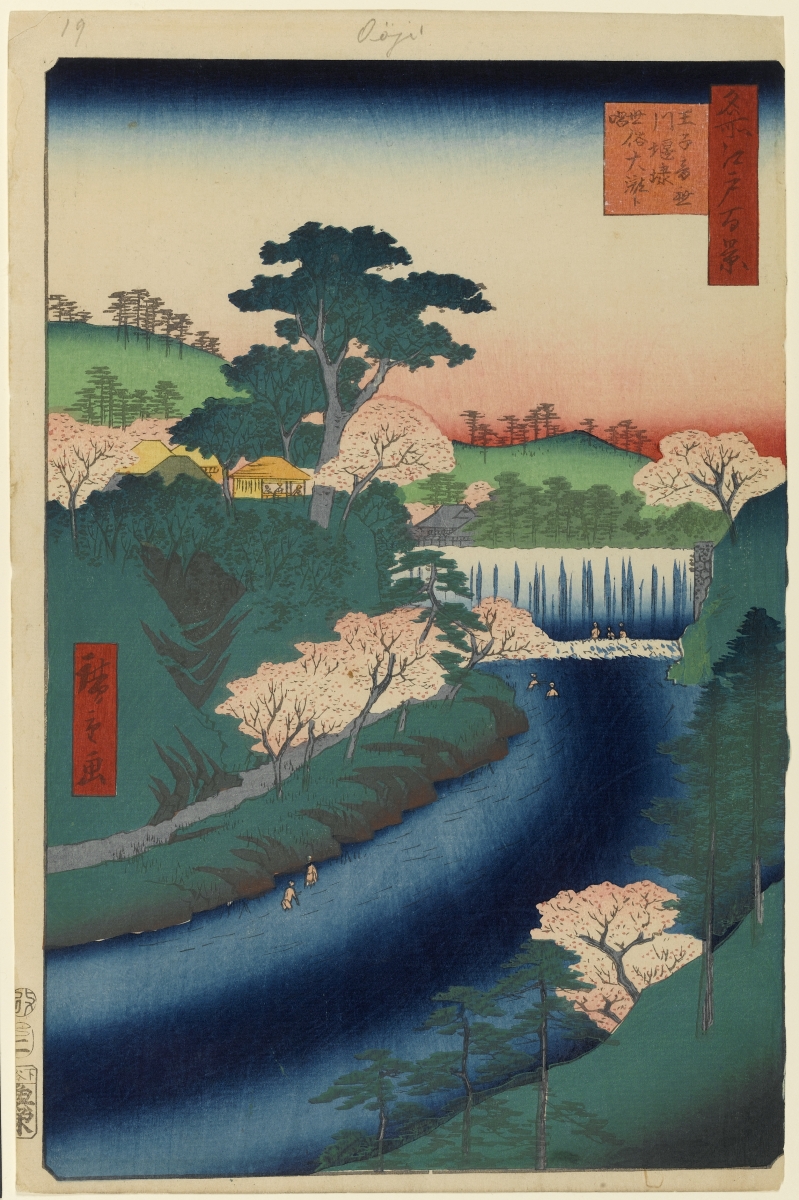2019年3月4日 月曜日 晴れ
山田康弘 縄文時代の歴史 講談社現代新書 2510 2019年
考古学的な手法を用いて社会の成層化プロセスを描いたモデルとしては、高倉が示した弥生時代の事例がシンプルで理解しやすい(高倉一九七三)。これを縄文時代の事例に適合させて改変すると以下になる。
I段階: 単一の埋葬小群で構成される、あるいは埋葬小群が複数存在しても、装身具・副葬品がない、もしくはそれらが些少な、等質的な墓地・墓域の段階。
II段階: 埋葬小群が複数存在し、共同墓地的な様相をもちつつも、特定の個別墓に希少性や付加価値性の高いものが集中する段階。特定の個人が発現する。
III段階: 埋葬小群が複数存在し、特定の埋葬小群に埋葬施設に対するエラボレーション(労働力の投下度合い)の高いもの、希少性や付加価値性の高いものが集中する段階。装身具・副葬品にも大きな差異が存在し、特定の集団が浮上する。
IV段階: 先の状況を踏まえて、墓域内から特定の埋葬小群が外に出る、あるいは特定埋葬小群から特定の個人たちが飛び出す段階。特定集団が突出し、エリート層が析出する。(山田、同書、p279-280)
**

作成: 2012年10月8日
縄文のビーナスと呼ばれる長野県棚畑遺跡出土の土偶、国宝。茅野市尖石縄文考古館にて。(ウィキペディアより引用)
*****
********************************************