2016年2月27日 土曜日 曇り
小林惠子 広開土王と「倭の五王」 讃・珍・済・興・武の驚くべき正体 文藝春秋 1996年
中国東北部に北魏(高祖)の威勢が届かなくなって、新たな騎馬民族系民族が跳梁することになった
*****
このように高句麗と百済の牟大が極東で覇権を争っていた四九〇年、北魏の実力者文明太后が死んで、再び東アジアの情勢は一変しつつあった。文明太后が亡くなると、ようやく高祖(孝文)が実権を握った。高祖は学問があり、仏教に傾倒していたが、そのためか脱騎馬民族志向が強く、何事も中華風を好んだ。・・高祖は・・四九四年、平城(大同市)から洛陽に首都を遷した。・・高祖の中華志向によって、北魏は中国を代表する国になったが、反面、中国東北部の幽州(現在の北京市周辺)から遼東にかけて北魏の威勢が届かないことになり、新たな騎馬民族系民族が跳梁することになった。その一つとして私がエフタル系と考える継体天皇(新羅智証麻立干)がある。五〇〇年に新羅を攻めた倭人とは靺鞨の居住する中国東北部から、佐渡を拠点として新羅を攻めた継体勢力だったと考えている。極東がこのような状態の時、「百済本紀」によると、牟大は殺されたという。・・ようするに牟大は暴君だったのである。(小林、同書、p234)
*****
補注 牟大 東城王 ウィキペディアによると・・・
東城王(とうじょうおう、生年不詳 – 501年)は百済の第24代の王(在位:479年 – 501年)である。『三国史記』によれば、諱を牟大、あるいは摩牟とし、第22代の文周王の弟の昆支の子とする。名と系譜については以下の異説がある。
『南斉書』では牟大とし、牟都(文周王?)の孫とする 。『梁書』では牟太とし、余慶(第21代蓋鹵王)の子の牟都(文周王?)の子とする
。『梁書』では牟太とし、余慶(第21代蓋鹵王)の子の牟都(文周王?)の子とする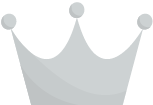 。また、牟都を牟大・牟太の転訛と見る説もある。ただし『三国史記』百済本紀・東城王紀末文では、古記に基づいて牟都という王はいないこと、牟大(東城王)は蓋鹵王の孫であり蓋鹵王を牟都とは言わないことを挙げ、『南斉書』の記述に対して疑義を唱えている。『日本書紀』では、蓋鹵王の弟で日本に来ていた昆支王(昆伎王)の第二子の末多王(またおう)とする。『三国遺事』王暦では、名を牟大または摩帝、余大とし、先代の三斤王の堂弟(父方の従弟)とする。子に武寧王。
。また、牟都を牟大・牟太の転訛と見る説もある。ただし『三国史記』百済本紀・東城王紀末文では、古記に基づいて牟都という王はいないこと、牟大(東城王)は蓋鹵王の孫であり蓋鹵王を牟都とは言わないことを挙げ、『南斉書』の記述に対して疑義を唱えている。『日本書紀』では、蓋鹵王の弟で日本に来ていた昆支王(昆伎王)の第二子の末多王(またおう)とする。『三国遺事』王暦では、名を牟大または摩帝、余大とし、先代の三斤王の堂弟(父方の従弟)とする。子に武寧王。
即位まで
『三国史記』では三斤王が479年11月に死去したので王位についたとするだけであるが、『日本書紀』雄略天皇23年(479年)4月条では、「百済文斤王(三斤王)が急死したため、当時人質として日本に滞在していた昆支王の5人の子供のなかで、第2子の末多王が幼少ながら聡明だったので、天皇は筑紫の軍士500人を付けて末多王を百済に帰国させ、王位につけて東城王とした。」と記されている。
治世
王位につくと直ちに、文周王を暗殺させた解仇の反乱を収めた真老を徳率(4等官)から兵官佐平(1等官)に昇進させ、内外の統帥権を委任した。また、首都熊津(忠清南道公州市)の在地勢力である燕氏、沙氏を重用して既存の政治体制を改革しようとした。対外的には、高句麗の長寿王が北朝だけではなく南朝にも朝貢して爵号を得たことを聞き、百済からも南斉に朝貢して冊封体制下に入ったが、高句麗の得た爵号に対しては評価の低いものに留まった。新羅との同盟(羅済同盟)を結ぶための使者の派遣も行っており、493年には通婚を要請して、新羅からは伊飡(2等官)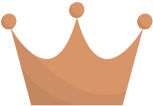 の娘が嫁いできた。翌494年には高句麗が新羅を攻めたところに救援を送って高句麗兵を退け、さらに495年には高句麗に侵入された際には新羅から救援が来て高句麗兵を退けている。このように新羅との同盟で高句麗に対抗する姿勢をとっていたが、501年7月には新羅に対しても警戒して炭峴
の娘が嫁いできた。翌494年には高句麗が新羅を攻めたところに救援を送って高句麗兵を退け、さらに495年には高句麗に侵入された際には新羅から救援が来て高句麗兵を退けている。このように新羅との同盟で高句麗に対抗する姿勢をとっていたが、501年7月には新羅に対しても警戒して炭峴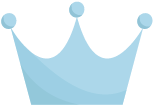 に城柵を築いた。498年8月には、耽羅(済州島)が貢賦を納めなくなったので親征のために武珍州(現在の光州広域市)に赴いた。これを聞いて耽羅は使者を送ってきて謝罪し、以後は百済に服属したとみられる。 倭国との関係では、東城王の即位以前に起きた二度にわたる百済と高句麗の戦い(455年と475年)において、古くからの同盟国であるにも関わらず倭国が百済を支援しなかったことを背景に東城王は倭国に対しては非友好的な態度を取っている[5]。
に城柵を築いた。498年8月には、耽羅(済州島)が貢賦を納めなくなったので親征のために武珍州(現在の光州広域市)に赴いた。これを聞いて耽羅は使者を送ってきて謝罪し、以後は百済に服属したとみられる。 倭国との関係では、東城王の即位以前に起きた二度にわたる百済と高句麗の戦い(455年と475年)において、古くからの同盟国であるにも関わらず倭国が百済を支援しなかったことを背景に東城王は倭国に対しては非友好的な態度を取っている[5]。
王権と国力の回復に努め、外征にも成果を挙げた東城王であったが、在位の晩年には暗君と化した。499年に大旱魃が起こって国民が餓えたが、国倉を開いて民に施そうとするのを許さず、漢山(京畿道広州市)の民2千人が高句麗領に逃亡した。それにも拘らず500年には王宮の東に高さ5丈もの臨流閣を築き、池を掘り珍しい鳥を飼うなどの贅沢にふけり、諫言をする臣下を遠ざけた。さらに同年にも旱魃があったが、側近とともに臨流閣で一晩中の宴会をするなどしていた。こうした状況のなかで501年11月、衛士佐平のハク加(ハクはくさかんむりに白)の放った刺客に刺され、12月に死去した。諡されて、東城王という。
脚注
^ 『南齊書』列傳 蠻東南夷 原文:「今以大襲祖 父牟都爲百濟王」(表曰:牟大は牟都を(亡)(義)父と呼んでいるとも読める。「牟都」=「三斤王」)
^ 餘映 – 餘毗 – 餘慶 – 牟都 – 牟太 (梁書)
腆支 – 毗有 – 蓋鹵 – 三斤 – 東城
^ 『三国史記』百済本紀では「伊飡」とするが、新羅本紀では「伊伐飡」(1等官)の娘としている。
^ 炭峴の比定地にはいくつかの説がある。全羅北道完州郡雲州面、忠清南道扶余郡石城面、忠清南道錦山郡珍山面、忠清北道沃川郡郡北面、など。
^ 沈(2003)
参考文献
『三国史記』第2巻 金富軾撰 井上秀雄訳注、平凡社〈東洋文庫425〉、1983 ISBN 4-582-80425-X
『三国遺事』坪井九馬三・日下寛校訂<文科大学史誌叢書>東京、1904(国立国会図書館 近代デジタルライブラリー)
『日本書紀』伴信友校訂 岸田吟香他 1883(国立国会図書館 近代デジタルライブラリー)
沈仁安『中国からみた日本の古代』 藤田友治・藤田美代子訳、ミネルヴァ書房、2003年
*****
補注 智証麻立干 ウィキペディアによると・・・
智証麻立干
Silla-monarch(13,17-22).png
各種表記
ハングル: 지증 마립간
漢字: 智證麻立干
発音: チジュン・マリッカン
日本語読み: ちしょう・まりつかん
ローマ字: Jijeung Maripgan
智証麻立干(ちしょう まりつかん、437年 – 514年)は、新羅の第22代の王(在位:500年 – 514年)であり、姓は金、諱は智大路、または智度路、智哲老。『三国遺事』では智哲老王・智訂麻立干とも記される。第17代奈勿尼師今の曾孫であり、先代の炤知麻立干とは再従兄弟となる。父は習宝葛文王、母は第19代訥祇麻立干の娘の烏生夫人。王妃は朴登欣伊飡(2等官)の娘の延帝夫人 。500年11月に炤知麻立干が死去したときに、子供がなかったので智大路が64歳で王位を継いだ。国号・王号の統一や軍制・官制などの整備を通して、新羅の国家形成を飛躍的に進めたと見られている。
。500年11月に炤知麻立干が死去したときに、子供がなかったので智大路が64歳で王位を継いだ。国号・王号の統一や軍制・官制などの整備を通して、新羅の国家形成を飛躍的に進めたと見られている。
治世
新羅には殉葬の風習が残っており、先代の王の炤知麻立干の死に当たっても男女5人が殉葬されていたが、502年3月に以後の殉葬を禁止することとした。503年10月には群臣の上奏を受けて、斯羅・斯盧・新羅などと称していた国号を新羅に、居西干・次次雄・尼師今・麻立干などと称した君主号を王にそれぞれ統一し、正式に新羅国王と号することとした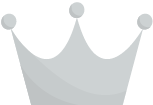 。
。
506年には国内の州郡県制を定めるとともに悉直州(現在の江原道三陟市)を置き、地方軍主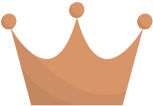 の官を設けて異斯夫(いしふ、이사부)を登用した。後に異斯夫を何瑟羅(江原道江陵市)軍主に任じ、于山国(鬱陵島)を服属させた。
の官を設けて異斯夫(いしふ、이사부)を登用した。後に異斯夫を何瑟羅(江原道江陵市)軍主に任じ、于山国(鬱陵島)を服属させた。
509年には王都金城に東の市場を開かせ、前後して市場を管理する市典(東市典)の官を設けた。また、514年1月には阿尸村(慶尚南道咸安郡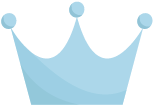 )に小京を置いて六部や南方からの入植を奨励し、小京の充実を図った。
)に小京を置いて六部や南方からの入植を奨励し、小京の充実を図った。
在位15年にして514年7月に死去し、智証と諡された。新羅の諡はこの智証麻立干(智証王)代に始まるとされる[5]。
脚注
^ 智証麻立干の系譜について『三国遺事』王暦では、父は訥祇麻立干の弟の期宝葛文王、母は訥祇麻立干の娘の烏生夫人、王妃は「迎帝夫人。倹攪代漢只登許作角干女」とする。
^ 1989年に発見された迎日冷水碑文によると、智証麻立干が503年9月時点では「王」ではなく「葛文王」と称されていたことが分かっている。
^ 軍主そのものは、第9代伐休尼師今の時代(185年)に中央軍主の官が設けられている。
^ 阿尸村については旧の阿尸良国(阿那加耶)にあたるものとして咸安郡に比定する説が有力であるが、他に昌寧郡とする説、慶州市(かつての月城郡安康邑)とする説もある。(→井上訳注1980 p.125)
^ 『三国遺事』紀異・智哲老王条においても智証王から諡が始まるとしているが、『三国遺事』王暦では法興王からのこととしている。
参考文献[編集]
『三国史記』第1巻 金富軾撰 井上秀雄訳注、平凡社〈東洋文庫372〉、1980 ISBN 4-582-80372-5
『三国遺事』坪井九馬三・日下寛校訂<文科大学史誌叢書>東京、1904(国立国会図書館 近代デジタルライブラリー)
*****
**********





