2016年7月19日 火曜日 曇り
レズリー・スティーヴン スウィフト伝 「ガリバー旅行記」の政治学 髙橋孝太郎訳 彩流社 1999年(原著は1882年ロンドンで刊行された)
スウィフトとガリバー旅行記:鋭利な風刺の刃は我が身をも苛む
スウィフトの風刺の力:軽蔑感を口にするための多数のシンボル
スウィフトの風刺の力
風刺の力はひとえにスウィフトが、それで以て、その大小にかかわらず激しい侮蔑感を表現したいと企図しており、そして我々に、しばしの間、同じ生き物の縮小版を見つめさせることによって自分の側に誘っているのである。(同書、p224-225) スウィフトが実際に意図したことは自分の同胞を軽蔑する人間に、その軽蔑感を口にするための多数の非常に有効なシンボルを提供することであった。(同、p225)・・しかし大多数の同胞の高潔さないし叡智に対する不信を知ってしまった皮肉屋は、自分の不信感を表明するための最適な隠喩を見出すであろう。かくて「ガリバー旅行記」は人間性の侮蔑者たちの気性に完全に合った風刺の百貨店なのである。(同、p225-226)
胸のムカつくようなイメージへの彼(スウィフト)の耽溺は、ある程度、彼の病んだ精神状態、恐らく、精神の事実的衰退の現れである。この特異さが一層際立つのは、スウィフトが個人的には徹底した潔癖症だったからである。・・彼は日常の会話においても品性を非常に大事にする人だった。(同、p227)・・彼は汚物への嫌悪感の烈しさ故に自らの敵対者たちを汚物でぬたくることになるのだ。(同、p228)・・彼の精神状態は衰え行く身体を凝視しながら肉体への侮蔑感をあおりたてる宗教の苦行僧のそれに酷似している。(同、p228)
大方の人間は人間嫌いの人間を、たとえその人の力に感服せざるを得ない場合でも厭うものである。(同、p231)・・そしてそうした好まれざる見解を詳細に開陳しさえする連中を我々は許すことはできない。(同、p231)
我々の好むのは、我々の欠点を見、そしてその上我々の困惑を哀れむ人間よりも、むしろ我々の欠点に盲目の人間である。我々が自分の属する種に対して抱く感情は自分自身に対して抱くそれと全く同じ種類のものである。我々が魅了されるのは、・・・(中略)・・・人当たりのいい楽天主義者(オプティミスト)なのである。(同書、p231)
・・「我々にとって心地よいことどもを話せ」、これは古今東西を問わずあらゆる予言者に向けられた人々の叫びである。そして人々の悪弊を攻撃するものは、悪弊を認めはしないが、しかしそれゆえにそれらが存在することを信じないことのほうを選ぼうとする人々の反感を買うことを覚悟しなければならない。・・・(中略)・・・そんなにも痛めつけられ、誤解されて、傷ついた魂を、非難するよりはむしろ哀れむ者もいよう。少なくとも我々は、かなわぬ運命のもとに、打ちのめされ、傷つき、そして押しつぶされ、にもかかわらず、いや増す自負心であらゆる敵対者たちと対峙し、そしてもはやその連中に損傷をあたえることができなくなってさえも、嘲笑によって自らを慰めた途方もないパワーのこの壮観さに、不快を催すよりはむしろ畏敬の念を覚えるのではないだろうか。(同、p232)
*****
補注 スティーヴン氏の立ち位置について:
原著者の Leslie Stephen(レズリー・スティーヴン)、彼の末娘は後に有名な女流小説家となったヴァージニア・ウルフである、とのこと、今回初めて知った。以前に、「灯台へ」を通読して、私は全く歯が立たなかったことを告白したことがあったが、今回のスティーヴン氏のスウィフト伝に関しても、著者のスウィフトに対する立ち位置が韜晦で簡単には判明できない。少なくとも煙に巻かれたような気持ちにさせられた。その原因は元々の原著者の文章スタイルに帰することかも知れないし、あるいは翻訳者(補注**)の翻訳文体に帰する事由かも知れない。後者の場合であれば、原書を紐解いてみるまでは勘違いが解けない。現時点での私は、スティーヴン氏はスウィフトに対して同情的ではなく、「窮地に自らを追いやる熟練した自己拷問者スウィフト」と評して厳しい批判の目を向けているように感じている。すなわち、スティーヴン氏のスタンスはスウィフトを忌避する普通の人間の側に立っている。「我々の好むのは、我々の欠点を見、そしてその上我々の困惑を哀れむ人間よりも、むしろ我々の欠点に盲目の人間である。我々が自分の属する種に対して抱く感情は自分自身に対して抱くそれと全く同じ種類のものである。我々が魅了されるのは、・・・(中略)・・・人当たりのいい楽天主義者(オプティミスト)なのである。(同書、p231)」と書かれているが、まさに、スティーヴン氏は、それらの人間性を冷静に広く見渡す優れた人物であることを自ら示しながらも、総合的にスウィフトに対して隠然と駄目出ししているように読み取れる。ただし、ヴァージニア・ウルフ同様、韜晦な話しの進め方でストレートには理解できない。何度も煙に巻かれているように感じられる。
*****
補注** 訳者の歴史理解に関して一言(いや、二言三言か):
本書の訳者は、1688年のウィリアムの「無血革命」(補注##参照)に言及して、手放しに英国人とアングロサクソン民族とを褒め称えて、「人間の自由主義にとって最も幸福となった事件」としている。つづけて、「英国人は、つまりアングロサクソン民族は、ノーベル賞の受賞者の数でもほかの民族を圧倒しているが(補注@@参照)、・・・(中略)・・・議会制民主主義という、古今未曾有の、すばらしく壮大な「カラクリ」を創出したということがこの民族の天才の最たるものである、ということができるであろう。 これは人類にとっての最大の福音なのである。」(同書、訳者あとがきにかえて、p265-266より引用)と述べている。
何ということだ! いやしくもスウィフトに関わる本の末尾に何という浅薄な歴史理解が表明されて、そのまま平然と出版されていることか、驚きである。
この訳者はガリバー旅行記を読んだことがあるのだろうか? この旅行記の中で議会制民主主義もキリスト教も知らなかった東洋の島国の住民が、アングロサクソン民族同胞に殺されようとしていたガリバーの命を救い隣人愛をもって遇した件を忘れてしまったのだろうか。この訳者はスウィフトの伝記を読んだことがあるのだろうか? スウィフトの時代のアイルランドの人々が「議会制民主主義の隣国」による圧政にいかに苦しんでいたかを、そしてスウィフトもこの現状を見つめ苦しんでいたことを、この訳者は忘れてしまったのだろうか。(補注**に対する補注***参照下さい)
この訳者は「七つの海を支配したこの議会制民主義国」の奴隷貿易と戦争の歴史を読んだことがあるのだろうか?「議会制民主主義のカラクリ」を通して民主的に多数決で決められた議決に基づき、アヘンを廃棄しようとした中国に襲いかかったこと(アヘン戦争)を、「この民族の天才」と言えば言えるのであろうか。強いて言えば、この訳者のような英語の素晴らしく達者な東洋のインテリの人々にまで「イギリスは民主主義の天才的な国」との幻想を真実と思い込ませるまでに世界の教育を支配していること、その仕組み自体はまさに天才的な「カラクリ」と言えるかも知れない。何ということだ!
補注者(すなわち私)は、この訳者の表明するような単純な英国人とアングロサクソン民族賛美に全く賛成できない。イギリスの初等教育の教科書にはそのように書かれているかも知れないが、たとえそうであっても、それをそのまま世界の初等教育教科書が受け入れてはいけないだろう。
*****
補注## 名誉革命について、ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/名誉革命 によると・・・
名誉革命(めいよかくめい、英: Glorious Revolution)は、1688年から1689年にかけて、ステュアート朝のイングランド王ジェームズ2世(スコットランド王としてはジェームズ7世)が王位から追放され、ジェームズ2世の娘メアリー2世とその夫でオランダ総督ウィリアム3世(ウィレム3世) がイングランド王位に即位したクーデター事件である。これにより「権利の章典」が発布された。実際には小規模の戦闘がおこり無血だったわけではないが、当時まだ記憶に新しいイギリスの内戦に比べると無血に等しいということで無血革命とも呼ばれている。清教徒革命と併せて「イギリス革命」と呼ぶ場合もある。
がイングランド王位に即位したクーデター事件である。これにより「権利の章典」が発布された。実際には小規模の戦闘がおこり無血だったわけではないが、当時まだ記憶に新しいイギリスの内戦に比べると無血に等しいということで無血革命とも呼ばれている。清教徒革命と併せて「イギリス革命」と呼ぶ場合もある。
偉大なる革命(Glorious Revolution)と呼ばれるのは、この革命によりイギリスのカトリックの再確立の可能性が完全に潰され、イングランド国教会の国教化が確定しただけでなく、権利の章典により国王の権限が制限され、イギリスにおける議会政治の基礎が築かれたからである。ただしイギリスのカトリック教徒にとっては以後数世紀に渡る受難の始まりであり、イギリスの国王およびその伴侶がカトリック教徒であることは現在でも禁止されている。
なお、オランダによるイギリス侵略という側面を強調する歴史解釈もある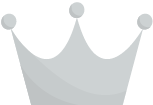 。しかし、現在では、名誉革命は内乱と外国の侵略が併存した「革命」であり、イギリス人の誇り及び介入したオランダ政府の政治的思惑などから、外国の介入の要素が意図的に無視されてきた、とされている。<ウィキペディアより、引用終わり>
。しかし、現在では、名誉革命は内乱と外国の侵略が併存した「革命」であり、イギリス人の誇り及び介入したオランダ政府の政治的思惑などから、外国の介入の要素が意図的に無視されてきた、とされている。<ウィキペディアより、引用終わり>
*****
補注## 「ノーベル賞の受賞者」に英米人が多いことに関して:
「英国人は、つまりアングロサクソン民族は、ノーベル賞の受賞者の数でもほかの民族を圧倒している」(同書、訳者あとがきにかえて、p265-266より引用・再掲)
間違いなく、ノーベル賞の受賞者の中には素晴らしい科学者・文学者が大勢いらっしゃるのは私も大いに認めたい。しかし、この輝かしい光の眩しさのために、人々にはその奥にある陰の暗さが見えなくなっている。
たとえば、ダイナマイト(多くの人命を失わせた発明品、戦争にも!使われる)による忌むべき名声(つまり悪評)を書き換えるために創設されたという、賞の創設者ノーベル自身による暗黒の誕生譚は象徴的である。創設由来のみに限らず、マスコミがとりわけ騒ぐこのノーベル賞というイベントには人々の歴史認識から大切な何かを隠し大切な何かを書き換える意図が見え隠れしている。暗い奥に見えるものを識らなければならない。
(1)このノーベル賞自体が、米国を含むヨーロッパの「お手盛りの賞」であり、その選考に深くかかわるイギリス(英米)に受賞者が多いことには「お手盛りのバイアス」がかかっている。つまり、同時に同じ成果を挙げれば英米人がノーベル賞をもらい易い。
(2)その「お手盛りのバイアス」を差し引いてもなお圧倒的に「ノーベル賞の受賞者」に英米人が多い。つまり、英米人の仕事はホンモノである。しかし、これは、英米が世界の富を支配し、そしてその富の余剰から生まれる学問や科学技術を牛耳ってきたのだから、英米がメジャーになるのは道理であり、いた仕方がないことを意味する。単にそれだけのことで、それ以上でもそれ以下でもない。つまり、ヨーロッパとりわけ英米に「天才」が輩出しやすいのは、いままでの歴史的事情が結果したことによる。ヨーロッパの文化的あるいは民族的優越性などに起因するものではない。
ヨーロッパによるアフリカ・アジア・南北アメリカからの500年に及ぶ収奪(収奪という呼び方を和らげるべきであれば、大きくアンフェアな交換から生み出されたもの)から得られた富の余剰的な部分が、学問や科学技術の研究開発に注ぎ込まれた。この富の蓄えがあって初めて、そして武力を背景に(あるいは露骨に前景に)してルネッサンス以来のヨーロッパの躍進発展がある。とりわけイギリスにおける産業革命以後の急速な科学技術の発展につながった。ヨーロッパの科学技術の圧倒的な優位性を支えてきたのは、この軍事力をもバックにして収奪された富の余剰部分である。
(3)このスウィフト伝の訳者にも感染が疑われるように、「天才」を輩出する優秀なアングロサクソン民族という神話、これの根底にもいわゆる「オリエンタリズム」言説(discourse)が根深く関わっている。(E.サイード、オリエンタリズム、ご参照ください) ヨーロッパとりわけ英米は、いわゆるマスコミを手中にして、言論界や学界を、そして世の中一般の人々の言説(discourse)を上手に身勝手に方向づけて行くことに長けている。マスコミがノーベル賞に関しては大きく騒ぎ、その頃になると毎年、連日繰り返し報道する陰で、たとえばアジアの小国の元首が授与するような賞は(よしんば金銭的にはほとんど横並びであっても)格下とされてほとんど顧みられない。ノーベル賞以外の賞に関しては(もしそれが有ったとしても)私たちがニュースで聞かないのは、オリエンタリズム現象のひとつである。たとえば仮に、ノーベル賞の倍額の副賞を授与するような賞をアジアやアフリカの国が創設したとしたらどうだろうか。その国自体が英米を代表とする「世界」から相当に睨まれることは目に見えている。ノーベル賞だけが世界一の権威でなければ(権威的な覇権からは)許されないのだ。ノーベル賞の権威に対抗するような賞を創設するアフリカ(またはアジアでもよい)の「独裁者」があれば、彼と彼の国は潰されるだろう。金額的には国家予算などに比べて科学者個人への賞金などは吹けば飛ぶような軽微なものではあるが、ノーベル賞というカラクリは、その背後に強力な軍事力という覇権に庇護されながら、圧倒的権威として他を睥睨しているのである。
(4)だから結局、一言で言うなら「ノーベル賞をもらえばエライ」という一般的な見解になる。が、管見では、良い学問・科学は、権威に寄り掛からず、地道に取り組んでゆくべきものだ。競争よりも協力ーーー私が常に学生やスタッフに語ってきた標語のひとつである。賞や賞金をもらうような功成り名遂げた大教授よりも、今現在の学問や研究に打ち込んでいる学生や若い科学者が、ずっと尊い行いを営んでいるのである。
*****
補注**に対する補注*** 友人から以下のようなコメントが寄せられた:
あなた(補注者)は、この訳者のコメントに対して「この訳者はスウィフトの伝記を読んだことがあるのだろうか?」といささか激しく論難されています。けれど、これは厳しすぎると思います。イギリスのアイルランドに対する圧政とスウィフトの行動に関しては、訳者自身がこの訳書の「あとがき」で具体的に解説しています。その解説の口調はアイルランド人やスウィフトに対して全面的には同情しきれない批判的な口調です。が、それは「この訳者はスウィフトの伝記を読んだことがあるのだろうか?」と非難されるほどの無知を露呈している訳ではありません。むしろある程度深くアイルランド史とスウィフトという人物を識りながら、アイルランド人やスウィフトに対して同情的ではない訳者自身の思想的立場を述べているのです。つまり、補注者との意見の相違は、歴史知識の有無の差ではなく、両者の思想信条の本質的な違いの問題です。従って、補注者がいくら手厳しく論難しても、当該訳者にとっては単なる水掛け論的攻撃に終わってしまうでしょう。
「イギリス議会制民主主義が人類全体の福音」だという当該訳者のような考え方は、実際、火元がイギリス自身から発信され喧伝されたスローガン(すなわちプロパガンダ)であるにせよ、むしろ、多くの主導的知識人に教科書的に受け入れられているキャッチフレーズであることは認めなければならないでしょう。それをあえて否定し、浅薄だと非難するのであれば、項を改めてかなり詳しく歴史を叙述していく方が生産的です。
あなたが「イギリス議会制民主主義の福音」のウソを追究したいのであれば、どうか歴史の事実に基づいた客観的な議論をしていただけますよう、期待しています。たとえば藤永茂さんが紹介されたアイルランド出身のケイスメント(補注$)の生涯に関して詳しく調べてみることから始められるのはいかがでしょうか。
けれど私には、あなたが本質的なところへと突っ込んでゆけば行くほど、イギリスやヨーロッパという枠に留まりきれないで、人間とその文明という普遍的なものの深みへと踏み込まざるをえないような予感があります。その現実は、東洋の島国に生まれ育ったあなた自身へ向けられる刃かもしれません。あたかも、スウィフトの風刺の鋭い刃が、宗教者生活者としてのスウィフト自身を痛めつけていったように、あなたの身を苛む危険なものでもあるような気がします。それでも、あなた自身がどうしても大切だと考えるなら、どうぞ怖れることなく深く分け入って欲しいと思います。私自身は、いつでも喜んでお話しをお聴きしたいと思います。
<以上、コメント終わり>
*****
補注$ ロジャー・ケースメント ウィキペディアによると・・・ https://ja.wikipedia.org/wiki/ロジャー・ケースメント
ロジャー・ケースメント(Roger Casement,1864年9月1日 – 1916年8月3日)は、アイルランドの人権活動家。イギリスの外交官を務め、ナイトの称号も与えられたが、後にアイルランド独立活動家になった。
ダブリン出身。外交官となりイギリス政府によってコンゴ自由国へ視察に赴き、そこで行なわれている暴虐を報告した。彼の報告書は、イギリス外相の前文を添えて各国政府に送付され、国際問題へと発展した。その後、リオ・デ・ジャネイロ駐在総領事となり、プトゥマーヨ河で発生した原住民虐殺事件の調査を命じられ、その地域で行なわれたゴム業者による原住民への搾取と虐待を報告した。1912年に辞職する。第一次世界大戦中の1916年、アイルランド義勇軍がイースター蜂起に使う武器を調達するため、ドイツ帝国のベルリンに渡ったが、帰国時に逮捕された。反逆罪とスパイ活動の罪により、ロンドンで絞首刑となった。
<以上、引用終わり>
補注 イースター蜂起 ウィキペディアによると・・・
イースター蜂起(イースターほうき、英語:Easter Rising、アイルランド語:Éirí Amach na Cásca )は、1916年の復活祭(イースター)週間にアイルランドで起きた武装蜂起である。日本では復活祭蜂起とも呼ばれる。この蜂起はイギリスの支配を終わらせ、アイルランド共和国を樹立する目的でアイルランド共和主義者たちが引き起こしたものである。1798年の反乱以降にアイルランドで起きた最大の反乱であった。
)は、1916年の復活祭(イースター)週間にアイルランドで起きた武装蜂起である。日本では復活祭蜂起とも呼ばれる。この蜂起はイギリスの支配を終わらせ、アイルランド共和国を樹立する目的でアイルランド共和主義者たちが引き起こしたものである。1798年の反乱以降にアイルランドで起きた最大の反乱であった。
蜂起はアイルランド共和主義同盟(IRB)の軍事部門によって組織され、復活祭週月曜日の4月24日から30日まで続いた。教師であり弁護士のパトリック・ピアースに率いられたアイルランド義勇軍、ジェームズ・コノリーに率いられたアイルランド市民軍、200人の女性連盟(Cumann na mBan)がダブリンの主要部を占拠して、アイルランド共和国の英国からの独立を宣言した。アイルランドの他の地域でも幾つかの行動が起こされたが、アッシュボーン兵舎(ミース州)への襲撃以外は小規模なものであった。
蜂起は7日間の戦闘の後に鎮圧され、指導者たちは軍法会議にかけられて処刑されたが、共和主義者の武力闘争主義をアイルランド政治の中核に置くことに成功した。1918年の英国議会総選挙(アイルランド島全土での最後の英国議会選挙)で、ウェストミンスターへの登院拒否と独立を標榜する共和主義者は105議席中73議席を得た。これは蜂起から2年足らずで起こったことである。1919年1月、この時まだ獄中にあった蜂起の生き残りを含むシン・フェイン党の国会議員は第一回アイルランド国民議会(First Dáil)を開催し、アイルランド共和国の樹立を宣言した。英国政府は新たに宣言された国家の承認を拒否し、アイルランド独立戦争へ突入することになる。
・・・(中略)・・・
・・これとは別にロジャー・ケースメントが1914年からドイツに滞在して義勇軍の代表として交渉を続けていた。ケースメントはIRBのメンバーではなく、IRBの義勇軍への浸透に全く気付いていなかった[19]。ケースメントの目的はドイツの収容所にいるアイルランド人捕虜によって旅団を編成し英軍と戦うことであり[20]、また貧弱な武装の義勇軍のためにドイツから武器を調達することも目的であった。前者は成功せず、また彼がドイツからの支援をとり付けた銃器の数は期待を下回るものであった。・・・(中略)・・・マクニールはショーン・マクディアマダから、IRBがロジャー・ケースメントとともに手配したドイツの武器の船荷が近いうちにケリー州に陸揚げされると明かされた時に何らかの行動が差し迫っていると確信させられた。彼はこのような船荷が当局に摘発されれば、義勇軍は弾圧されることになり、必然的に義勇軍は自衛行動に出ざるを得なくなることは疑いないと思った[23] 。
ドイツから提供された支援に失望していたケースメントはドイツの潜水艦でアイルランドへ戻ったが、トラリー湾のバナ海岸に上陸してすぐに逮捕されてしまった。武器はノルウェーの漁船に偽装したドイツ船オウド号に積み込まれていたが、現地の義勇軍が会合に失敗し、英海軍に発見されて自沈している。
翌日、マクニールは武器を積んだ船が自沈したことを知り、本来の立場に立ち戻った。同じ考えを持つ他の指導者たち、特にブルマー・ホブソンとザ・オラヒリーの助けを得て、彼は義勇軍に対し日曜日の全ての行動を取り消す中止命令を出した。これは蜂起を一日延ばしただけであったが、蜂起に参加する義勇兵の数を大幅に減らす結果となった。
ドイツ本国と駐米ドイツ大使館との無線通信は英海軍によって傍受され、海軍本部40号室で解読されており、武器の密輸とケースメントの帰還そして蜂起を行う復活祭の日付は海軍情報部によって既に察知されていた[24]。この情報は4月17日にアイルランド次官マシュー・ネイサンへ渡されたが、情報源が秘匿されていたため、ネイサンは懐疑的だった[25]。オウド号の摘発とケースメント逮捕のニュースがダブリンに届き、ネイサンは総督のウィンボーン卿と対策を協議した。ネイサンは市民軍の司令部があるリバティ・ホールおよび義勇軍の建物があるファザーマシュー・スクウェアとキメージを急襲することを提案したが、ウィンボーン卿は指導者たちの一斉逮捕を主張した。結局、復活祭の月曜日まで行動を先延ばしすることになり、ネイサンはロンドンのアイルランド大臣オーガスティン・ビレルに行動の承認を求める電報を打った[26]。ビレルが行動を認める返電を送ったのは1916年4月24日月曜日であり、蜂起はすでに始まってしまっていた。
・・・(中略)・・・
ドイツから武器を運び込もうとしたロジャー・ケースメントは国家反逆罪で裁判にかけられ、8月3日にペントンビル刑務所で絞首刑となった。
・・・(中略)・・・
<以上、引用終わり>
*****
********************************************






